あらすじ
京都大学を出て心理学の博士号を得たハカセ(東畑開人)は、通常であればアカデミア(大学)の世界で働くところを「現場に行って一流の臨床心理士になるのだ」と言って悪戦苦闘の職探しの末、沖縄の精神科デイケア施設に職を得た。しかしそこは統合失調症の相手をする、ハカセには苦しい、ふしぎの国であった。ウサギの穴におっこちたハカセは考える。
「ケアとは何か、セラピーとは何か」
臨床を本当に経験して、悩み抜いた博士だからこそ書ける。臨床の実際と問題の提言。
ケアとセラピーの覚書。大感動スペクタクルの学術書。

ポイント
学術書である
この本は臨床の現場を読みやすい体験記の形式で書いていると同時に医学書院(かなり正当な医学系の出版社)から出ている学術書でもあります。そのため、本の中には何度も学術的な見解や深い洞察などが含まれており、それらの参照元なども詳細です。臨床心理、および医療に携わる人であれば参考になる記述が多いのではないでしょうか。
臨床心理以外にもつながる
またこの本は臨床心理学のケアとセラピーについての覚書でもあると同時に職場に「居られない」という心理や、ある人間関係のなかに「居続ける」という試練への示唆に富んだ見解も示してくれています。以下、私が興味をもった文章の引用とその解釈。
ケアとセラピーの日常

この本の前半ではデイケアの日常とその心理的な考察を記しています。
「ただいる」というだけでも練習がいる
僕が机の木目を数え、ジュンコさんが調理の手伝いをしていたのと同じだ。環境に実を預けることができないときに、僕らは何かを「する」ことで、偽りの自己をつくり出し、なんとかそこに「いる」ことを可能にしようとする。生き延びようとする。
つまり、「どこにいてもいい」という自信をつけないと、偽りの「する」をつくり出さなければ行けないという心理になり「いるだけ」という行為が苦しくなる。
逆に言うならば、「いる」ためには、その場になれ、そこにいる人たちに安心して、身を委ねられないといけない
その場に慣れ、安心することで、自信につながる。今の職場がつらく転職や人間関係をリセットするにしても、まずはこのことを自覚することが重要だと感じました。
暇して退屈になれるというのは実は素晴らしい
退屈できないハエバルくん(患者さん)は空虚のなかにいなかったことになる。(中略)空間に「何か」が充満していたのだ。たとえば、幻聴。それから被害妄想。それは何も統合失調症の人だけに限らない。不登校になった子供や会社を休んでしまったサラリーマンは、みんなの視線が痛い。すると、退屈なんかしていられない。
つまり暇して退屈できる場所や人間関係があって、そこに居続けられるということは心理的にはとても重要なことということです。自分のスキルを向上させなければいけない、とかもっと違う自分にならなくてはいけない、という気持ちも大事ですが、まずは「今の自分でもいい」という自己肯定感や自己承認が暇して退屈になれるという心理を作り出すのだと考えました。
存在感を誇示しない
そう、人は本当に依存しているとき、自分が依存していることに気がつかない。(中略)子供がいちいち母親のしていることに感謝しているとするなら、それはなにか悪いことが起こっている。依存がうまくいっていないということだ。依存労働は当たり前のものを、さも当たり前のように提供することで自分が依存しているということに気がつかせない。
大人の仕事とは本質的には制御するということ。制御はうまく言っているときには気が付かない。
大人が自分の仕事の重要さを誇示しようとしたら、制御を定期的に止めて困らせようとする。
ケアされることで、ケアする
デイケアで僕はケアされる。体調が悪いんじゃないかと心配され、飴をもらう。バドミントンでミスしたらリュウジさん(患者さん)がカバーしてくれる。しかも励まされる。ヤスオさんは拾ったタバコをくれる。僕はすべてをありがたく受け取る。いやウソだ。ありがた迷惑なことが多い。でも受け取る。ケアを受け取るのも仕事なのだ。
(中略)そういうことについて、真正面から考えてきたのが、ユング心理学の「傷ついた治療者」っ理論だ。じつはセラピーのなかでも、ケアすることとケアされることがあべこべになることがよく起こる。
ケアとは何か、セラピーとは何か

後半では、ケアとは何か、セラピーとは何かやブラックデイケアという問題を扱っています。できるだけ多くの人にこの本の内容と素晴らしさをお伝えしたいため、大きなネタバレにならない範囲でこの本の後半について書かせていただきます。
最終章へ
ウサギの穴に落っこちて不思議の国についたハカセは、わずか4年で先輩がみんな辞めていってしまい、自分もまた体調を崩してしまう。物語の裏側で何が起こっているのか、真犯人は誰なのか、ケアとセラピーという二人の主人公のちからを借りて本書は最終章へ向かう。
ブラックデイケア
次々と人が入れ替わり、使い捨てにされていく。代わりはいくらでもいるから、「いる」がないがしろにされる。ブラックなものは、「いる」を軽視する「いられない」場所に生じる。
小林エリコ氏のエッセイ「この地獄を生きるのだ」を引用して、国からの補助が出るため患者が診療報酬目当てのデイケア経営の道具になっていることを提言する。どんなにデイケアに気持ちや欲望を満たすものが準備されていても、クリニックにしか行くところがない彼ら、彼女らは地獄と感じる。
デイケアはたしかに患者さん(メンバーさん)の役に立っている一面もあるが、その裏側には国からの補助金をもらうために患者さんをクリニックに入れるという力が働いている。患者さんの相手はつらい仕事であるため割の良い給料でスタッフを集めるが仕事がつらいためスタッフの離職率は高い。また患者さんの方も社会からクリニックという居場所を与えられてそこ以外行き場所がないと感じてしまい、つらくなってしまう。
まとめ
「ただ、いる、だけ」。
居場所をつくるためにこの本に書かれたことを語り続けることが大切だと感じました。

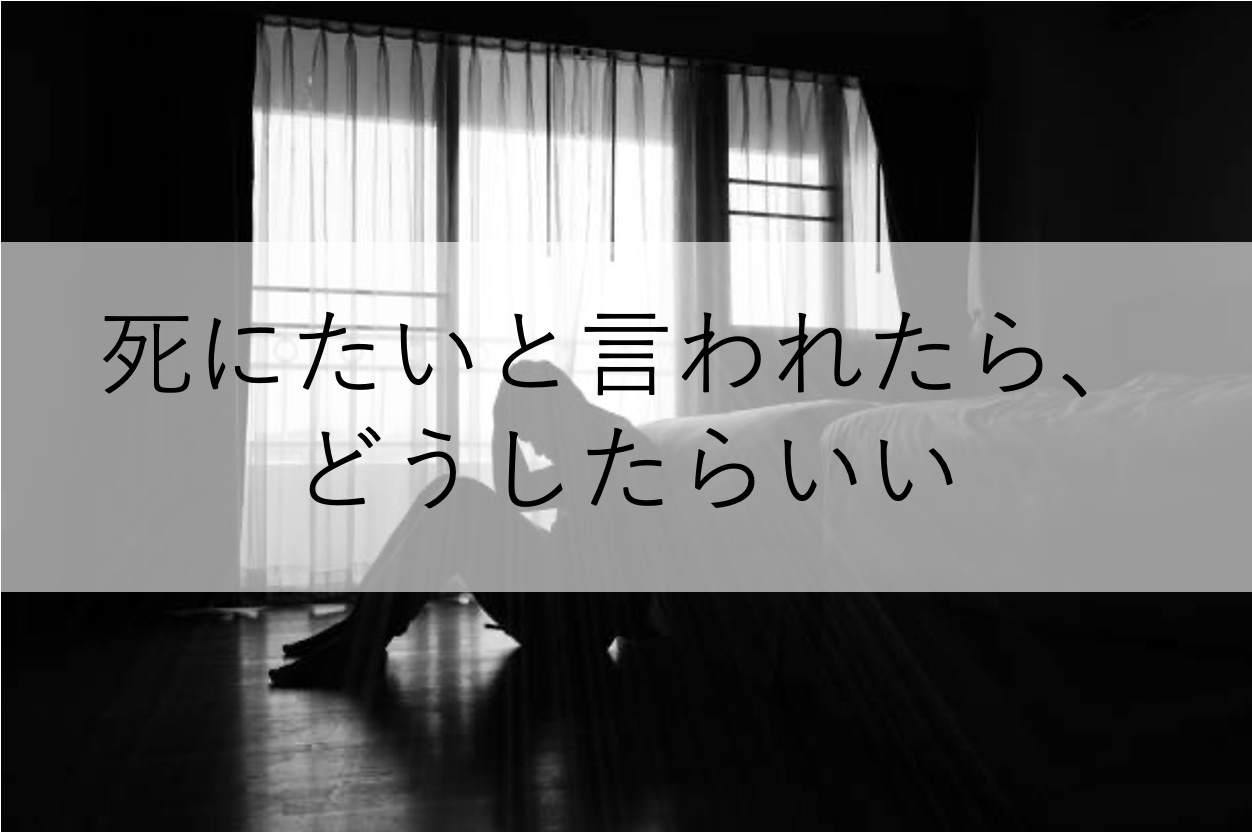

コメント